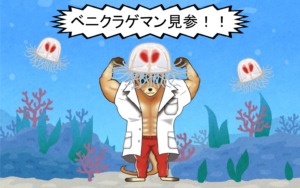ノウキン
ノウキン今日の朝ごはんは卵かけご飯!
朝ごはんには卵がかかせないっす!



いつも美味しそうに卵を食べてくれてありがとうザマス!



いきなりニワトリが出てきた!?
茶色ってことは、赤玉の卵を産む『ボリスブラウン』っすか?



よくご存知ザマス!
だけど、毎日食べている卵のことは理解してるザマスか?



言われてみると、毎日食べてる割にニワトリの卵のことよく知らないっすね(汗)



なら、今回はニワトリの卵について教えるザマス!
まずはこの本をお読みなさい!
『目玉焼き』、『スクランブルエッグ』、『卵かけご飯』など多くの人が毎日のように食べているニワトリの卵。
しかし、そんなニワトリの卵について知っている人は多くありません。
本記事は、以下の書籍を参考に意外と知られていないニワトリの卵について紹介します。
著者の森 誠氏は静岡大学農学部の名誉教授であり、これまでに家禽の産卵生理、卵黄膜、そして排卵とステロイドホルモンの関係などの研究をしています。
書籍には卵についてだけでなく、以下のようなニワトリの歴史についても書かれています。
- ニワトリの祖先は現在もインドやベトナムに生息している『セキショクヤケイ』という野鳥。
- ニワトリは約5000年前にインドで初めて家畜化された。
- 日本へは弥生時代に渡ってきたと言われている。
また、「赤玉と白玉のどちらがいい卵なのか」などニワトリの雑学も書かれており、楽しく学べる一冊です。



言われてみれば当たり前だけど、ニワトリは元々野鳥で家畜化と改良されて今の姿なんっすねー



現代でも肉用と採卵目的で日々改良されてるザマスよ。
日本だと『名古屋コーチン』とかが有名ザマス。



名古屋コーチン、美味しかったなー





そろそろ本題に行くザマスよ!



危うく名古屋コーチンで頭がいっぱいになるところだったっす(汗)
本題はニワトリの卵でしたね!
毎日食べているニワトリの卵について知りたい・研究してみたい人に参考となる記事ですので、最後までお読みいただけますと幸いです。
ニワトリの卵巣・卵管



ニワトリの卵って結構硬くて産むのが大変な気がするっす。
卵を産むためにニワトリの体は特別な構造になっているんすか?



もちろん人間とは構造が違うけれど、関わってくる臓器は『卵巣』と『卵管』で同じザマス。
ニワトリが卵を産むのに関わる臓器は、大きく分けて『卵巣』と『卵管』の2つです。
まず、卵巣には黄身の元になる『卵胞』がブドウのようにつらなって存在しています。
卵胞は7〜12日かけて肝臓で生成された卵黄物質が血液を通して卵巣に蓄積して生成されます。
成熟した卵胞から順番に卵巣から卵管へ排卵されるようになっており、最大卵胞(最も成熟した卵胞)が排卵された翌日に第2卵胞が最大卵胞に成長します。
ちなみに、ニワトリを含む多くの鳥類の卵巣はなぜか左側だけ発達しており、右側は退化しています。



ニワトリの卵巣には、約1万個の卵胞が存在していると言われているザマス。



1万個も卵を産めるポテンシャルがあるってことっすか?



卵が卵管を通るのに1日以上かかるし、寿命も長くて10年と考えると1万個は物理的に無理ザマスね。
卵管は『漏斗部』・『膨大部』・『峡部』・『子宮部』・『膣部』から形成されており、全長は約70 cmです。
漏斗部〜子宮部の各部位で卵が徐々に形成されていき、最終的に膣部から放卵されます。
各部位での卵の形成段階と通過時間を以下にまとめます。
- 漏斗部:受精・『カラザ』形成(約15分)
- 膨大部:『卵白』形成(約3時間)
- 峡部:『卵殻膜』形成(約1.5時間)
- 子宮部:『卵殻』形成(20時間)



子宮部を通るのに20時間もかかるなんて大変っすね(汗)



それだけ硬い卵殻を形成するのに時間がかかるってことザマス!



毎日大変な想いで卵を産んでるニワトリさん達にマジ感謝っす(泣)
卵の構造



次は卵の構造について教えてあげるザマス!



さっき出てきた卵の部位のことよく知らないので助かるっす!
以下の画像は、ニワトリの卵の構造をまとめた画像です。


外側から「卵殻→卵殻膜→外水溶性卵白→濃厚卵白→内水溶性卵白→卵黄」の順に構成されています。
最も外側に形成される『卵殻』は炭酸カルシウムが主成分であり、水分はほとんど含まれていません。
これにより一定以上の強度が得られ、卵の中身を守ることができます。
また、卵殻には『気孔』という小さな穴があり、気孔から酸素の取り入れと炭酸ガスの排出(ガス交換)をすることで胚が呼吸可能になります。



卵殻に気孔があるなんて知らなかったっす(汗)



気孔がなかったらヒナちゃんが呼吸できないからね。
まぁ、食用の卵には必要ないザマスけど。
卵殻に密着している『卵殻膜』は薄さ0.07 mmの膜であり、主成分はタンパク質です。
卵殻膜には、卵殻では守りきれない微生物や紫外線などから胚を守る役割があります。
産卵して時間が経過した卵は時間経過と温度変化により卵殻膜が密着していない空間が発生し、『気室』という空間ができます。



卵殻膜は卵殻で守りきれないものから胚を守るのが役目ザマス。



最後の砦って感じっすね!
卵の内部の大半を占める『卵白』の主成分はタンパク質であり、『外水様卵白』・『濃厚卵白』・『内水様卵白』・『カラザ』の4層から成ります。
水溶性卵白と濃厚卵白は粘度が異なり、粘度が低いのが水様生卵白、粘度が高いのが濃厚卵白と区別できます。
卵全体に占める割合は濃厚卵白の方が多く、水分保持やカビ等の繁殖の抑制など腐食を防ぐ役割を果たします。
また、カラザは胚である卵黄を固定し衝撃から守る役割をしています。



カラザって白い糸みたいなやつっすよね?
あれって食べても大丈夫なんすか?



結論、カラザを食べても問題ないザマス!
カラザに含まれるシアル酸に害はないザマス。



これで遠慮なく卵全体を食べられるっす!笑
卵の中央にある『卵黄』には、卵のほとんどの栄養が集中しています。
タンパク質・脂質・ビタミンなどヒナの成長に必要な成分が満遍なく含まれています。
卵黄に豊富な成分が含まれているため、卵は『完全栄養食』と言われています。



卵黄を食べることでタンパク質・脂質・ビタミンなど必要な栄養をまるっと摂取できるんっすね!



だから、卵は『完全栄養食』と言われているザマス!
あなたの筋肉も毎日卵を食べてるおかげかもしれないザマス。



確かにそうかもしれないっす!
卵を産んでくれるニワトリさんに再度マジ感謝(泣)
ニワトリは毎日卵を産めるのか



卵を必ず毎日食べれるようにニワトリを飼うことに決めた!
そうすれば365日産みたての卵を食べられるっすね!



ニワトリは毎日卵を産むわけではないザマスよ!
あくまで、「ほぼ毎日」ザマス!
再び卵管の通過時間を確認してみましょう。
- 漏斗部:約15分
- 膨大部:約3時間
- 峡部:約1.5時間
- 子宮部:20時間
上記の卵管の通過時間に加えて産卵後から次の排卵までに約30分かかります。
そのため産卵の間隔は24時間30分〜25時間30分かかり、産卵時刻は毎日30分〜1時間30分ずつ遅れます。
産卵時刻が遅れてくるとニワトリは卵を午後に産むようになり、さらに遅れてくると夜になってしまいます。
しかし、ニワトリは夜には卵を産まず休み、翌日の朝から産卵を再開してリズムを取り戻します。



次の産卵までに24時間以上かかるから、産卵時間が毎日ズレていくんっすね。



数日間連続して卵を産むと、1〜2日産卵をお休みしてリズムを取り戻す場合もあるザマス。



そうなると卵を毎日産んでもらうのは無理かー(泣)



そうザマス。
それに、ニワトリが卵を産むには光も重要ザマス。
ニワトリは日照時間で季節や時刻を把握しており、日照時間の短い夏至以降になると産卵数が減少します。
産卵数が減少する理由としては、産卵に必要なホルモンの分泌量も減少するためです。
養鶏場では、産卵数の減少を防ぐために照明で光の時間をコントロールしてほぼ毎日産卵できる環境にしています。
このように産卵の環境を整えた場合、ニワトリは1年間で平均して280〜300個の卵を産みます。
1年間で365個以上産卵した記録もありますが、かなり希少なケースです。



産卵数は日照時間にされるなんて知らなかった!
日照時間が短い冬になると日本から卵が消えるのかと焦ったっす(汗)



養鶏場では照明で光の時間をコントロールしてるから問題ないザマス。
品種改良と養鶏家さん達の努力によって卵がなくならないように生産量を管理できているザマスよ。
エピローグ



ニワトリの卵のこと少しは理解してくれたザマスか?



とりあえず、1年間毎日卵を食べるためにはニワトリを2羽以上飼う必要があることはわかったっす!



そんなに毎日卵を食べたいザマスね(汗)



だって卵はめっちゃ美味しいっすもん!
ニワトリさん達には本当に感謝してるっす!



そう言ってもらえて来た甲斐があったザマス!
それじゃあ、私は仕事に戻るザマス。



ボリスブラウンさん、ありがとうございました!
本記事ではニワトリの卵の話が中心でしたが、参考書籍には他にもニワトリの話題が数多く書かれていますので、興味がある方はぜひ一読ください。
今回の記事はこれで終わりです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!